仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
「GNU宣言」発表から30周年を迎える
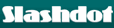
1985年3月にRichard M. Stallman氏が「GNU宣言」を発表してから、30年が経過する。The New YorkerではStallman氏へのインタビューを交え、GNU宣言30周年を祝う記事を掲載している(The New Yorkerの記事、 本家/.)。
Stallman氏は現在も開発者に多大な影響を与えている。彼を崇拝する開発者の中には、Stallman氏の努力がなければ現在とは異なる人生を送っていただろうと話す人もいるそうだ。しかし、このような人々も皆iPhoneを持っており、Stallman氏の教えに従っていないようにも見える。Stallman氏は携帯電話を「ビッグブラザーのための道具」と呼び、自身は携帯電話を所有していない。この点についてどのように思うか尋ねたところ、「彼らが自分たちの自由を守る必要があることに気付いていないなら、いずれは持つのをやめることになるだろう。」と答えたという。
Stallman氏のフリーソフトウェアの夢が広く普及しているとはいいがたいが、多くの組織や個人がGNU/Linuxを導入するなど、彼の考えはさまざまな点で成功し続けているといえる。Stallman氏にその気があれば、シリコンバレーの大富豪のように大金持ちになれたはずだ。Stallman氏にとっての幸せが豊かさや快適な生活を送ることに基づかないなら、幸せは何を意味するのかという質問に対しては、「私にとっての幸せは、自分自身が満足できることと、愛があることだ。」とし、「自分自身を満足させるため、私は自分が価値があると信じることを実行しなければならない。」と述べたとのことだ。
スラッシュドットのコメントを読む | スラッシュドットにコメントを書く | オープンソースセクション | オープンソース | GNU is Not Unix
ビジネスの好機 米加州と日本、環境技術で覚書

2014年9月5日、日本政府は約3880万人の人口と約235兆円の国内総生産(GDP)を持つ「政府」と、環境関連技術での協力拡大に向けた覚書を交わした。相手は国ではなく、カリフォルニア州政府。両政府は気候変動の危険性を認識して、高速鉄道や電気自動車(EV)、再生可能エネルギーなどの分野で協力することで同意した。エネルギー貯蔵、排出ゼロ自動車(ZEV)、電動自動車の給電インフラ、水の節約技術なども含まれる。
■環境負荷減らす21世紀型インフラ技術を開発
カリフォルニア州には米テスラ・モーターズなど環境関連企業も多い(イーロン・マスク最高経営責任者)
筆者の周りには、日米のビジネス環境について観察しているビジネスマンが多い。両政府が覚書を交わしてから約半年が経つが、その存在を知っている人が少ないのは残念だ。
覚書の意味は、日本とカリフォルニア州は21世紀に求められるインフラを構成する技術の実現で協力する、ということだ。今世紀に入って、中国やインドなど発展途上国の経済環境は改善の一途をたどっている。こうした国々は当然、先進国と同レベルの生活水準を目指す。だが、彼らの希望を満たすために、多くの環境危機を起こした20世紀のインフラ技術を利用することはもうできない。環境負荷を減らす21世紀が要求するインフラの技術開発には重要なビジネスチャンスが広がる。
この分野で、カリフォルニアと日本が組むのは自然だ。天然資源が少なく人口が多い日本では「節約」という文化が根強い。福島の原子力発電所の事故が契機とはいえ、再生エネルギーを普及させる重要性も浸透した。何より日本の企業や大学には、21世紀型インフラが要求する基本の技術や製造ノウハウが豊富だ。
■米加州、20年までに電力の33%を再生可能エネに
一方のカリフォルニア州は、かなり以前から環境活動に関心がある人々が米国の他の州に比べ多い。米連邦議会は環境規制や再生可能エネルギーへの投資に批判的な保守党が支配している。だがカリフォルニア州政府は20年までに電力の33%を再生可能エネルギーに切り替えるなどの政策を積極的に推進している。さらに、シリコンバレーならアップルやグーグルなどIT(情報技術)企業が、必要とする電力を再生可能エネルギーから得るために投資を積極化するなど、環境問題に関心が高い企業も多い。何より、シリコンバレーには、新しいテクノロジーを素早く市場で成功させるマーケティングのノウハウが豊富だ。
人口の過半数が37歳以下 米マーケティング最新事情

日本では高齢化が進み、企業が中高年を主要顧客に想定する場合が多い。一方、米国は先進国には珍しく全人口の過半数が37歳以下の若者であり、今後もその割合は増えると考えられている。そして、2020年にはこの世代の市場規模が1兆4000億ドル(約152兆円)以上になると見込まれている。そして若者人口の増加により、より一層の経済発展が期待できる。これらの統計を見ても、米国の消費者市場は日本と異なり、今後も若者が中心であり続けることが約束されている、とも言えるだろう。
米国の全人口の過半数を37歳以下の若者が占める(2014年12月、カリフォルニア州ロサンゼルスのショッピングセンター)=ロイター
商品やサービスを提供する企業は、若者に受ける商品開発やマーケティングが必須になる。若者の心をつかめれば,その後の人生を通じて利用してもらえる。そして、最近の若者が企業のブランドに接する機会が最も多いのがインターネットだ。統計によると、実に若者の3分の2がネットを通じてブランドとのつながりを感じているのに対し、現在の企業発のキャンペーンに満足しているのはわずか3分の1にとどまっている。
このギャップは、企業がネットを通じて消費者に配信しているコンテンツの内容によるところが大きい。現代のネットユーザーは平均で1日に5000のマーケティングメッセージを受け取っており、自分の興味や生活パターンに合致した内容だけを無意識のうちに選別している。もしそのコンテンツが消費者層にとってふさわしい、もしくは役に立つものであれば、購入まではあと一歩だ。一方で、ユーザーの興味に合致しない広告を配信しても、あまり効果はない。
では、米国の若者はどのような方法で商品やサービスに接するのか。統計によると、米国における37歳以下のインターネットユーザーの71%が米グーグルの検索サービスを、65%が米フェイスブックを通じてブランドコンテンツに接している。写真投稿・共有サービスでも24%がピンタレストを、23%がインスタグラムをきっかけに、ブランドに接していると答えている。グーグルの検索サービスを除いて、若者を中心とした消費者は企業からの情報以上に友人や他のユーザーが提供する情報を元に、商品やサービスといったブランド情報に接している。
企業統治の新ルールに「環境問題」 株主も関心

金融庁と東京証券取引所が共同事務局を務める有識者会議は5日、コーポレートガバナンス・コード原案を公表した。東京証券取引所では、現在ある有価証券上場規程を改正して、上場会社コーポレート・ガバナンス原則を廃止し、6月1日からコーポレートガバナンス・コードを市場第1部、市場第2部、マザーズ、ジャスダックの上場会社全社に適用する予定としている。
報道などでは「独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきであり、上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべきである」(原則4―8)という一文に関心が集まっているが、注目点はこればかりではない。
「上場会社は、自らが担う社会的な責任についての考え方を踏まえ、様々なステークホルダーへの価値創造に配慮した経営を行いつつ中長期的な企業価値向上を図るべきであり、こうした活動の基礎となる経営理念を策定すべきである」(原則2―1)や「上場会社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー(持続可能性)を巡る課題について、適切な対応を行うべきである」(原則2―3)は、環境問題対応がコーポレートガバナンスの構成要素であるという裏書を得たという点で画期的な出来事であろう。
本コードの手本となった、経済協力開発機構(OECD)コーポレート・ガバナンス原則(2004年制定)にも、コーポレート・ガバナンスにおけるステークホルダー(利害関係者)の役割に関する章はあるが、社会・環境問題への対応を、これほど真正面からは記述していない。
本コード(原案)の各原則(基本原則・原則・補充原則)は、企業にとっての義務ではない。ただ、これらの中に、自らの個別事情に照らして実施することが適切でないと考える原則があれば、それを「実施しない理由」をコーポレート・ガバナンス報告書で説明することが求められることになる。その意味で、企業の環境問題対応への確実な追い風となろう。
CO2の地下貯留、万一漏れ出たら 実験で検証

温暖化ガスの排出を減らすには発電所や工場から出る二酸化炭素(CO2)の回収・貯留(CCS)が不可欠とされる。地下深くに閉じ込めたCO2が万が一、漏れ出たらどうなるか。実際に地層中に漏出させ、その広がり方や影響を見る国際プロジェクトの結果がまとまった。コンピューターで漏出を再現する数値実験と合わせ、万全の対策づくりと安全性確保に生かす。
英国スコットランドの保養地に近いアードマックニッシュ湾で、海底下約11メートルからCO2を放出する実験に日英の研究者が取り組んだ。「CO2地層貯留が生態系に起こしうる影響の定量化と監視」を意味する英語の略称から「QICS」計画と呼ばれる。
英政府系機関が2010年から4年間に200万ポンド(約3億7000万円)を投じ、プリマス海洋研究所や地質調査所、サウサンプトン大学などが実行した。日本からは東京大学や地球環境産業技術研究機構(RITE)、電力中央研究所などが参加。経済産業省が11年度から3年間に1億円を拠出した。
プロジェクトでは海底下の地層内にCO2を送り込んで漏出させ、最適な測定法を検討した。海洋中のCO2の拡散も調べ、生物への影響の有無を知る手掛かりを得るのが目的だ。
陸上から計約4トンのCO2を海底下に送り込んで放出し、約1年間にわたり周辺のCO2濃度などを測った。自動測定に加えて、ダイバーによる観察や測定も試みた。
実験中は海底からCO2の気泡が上昇するのが見え、音響センサーでその流れを定量的にとらえられた。CO2が水中に溶けることで生じる酸性度の変化は場所によるばらつきが目立った。水中のCO2濃度は放出場所の真上付近の海底近くでのみ増えた。
測定データは潮の満ち引きなどによって変化する。自然変動と漏出したCO2の切り分けの難しさが浮き彫りになった。生態系への影響は漏出場所の近くで一部の微生物が減ったが、3週間以内に元の状態に戻った。
実際の漏出量はもっと多くなって、影響も増す可能性があるが、範囲は限られるだろうとしている。
