仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
X線天文衛星「すざく」、2つの銀河団が秒速1500kmで衝突している現場を観測
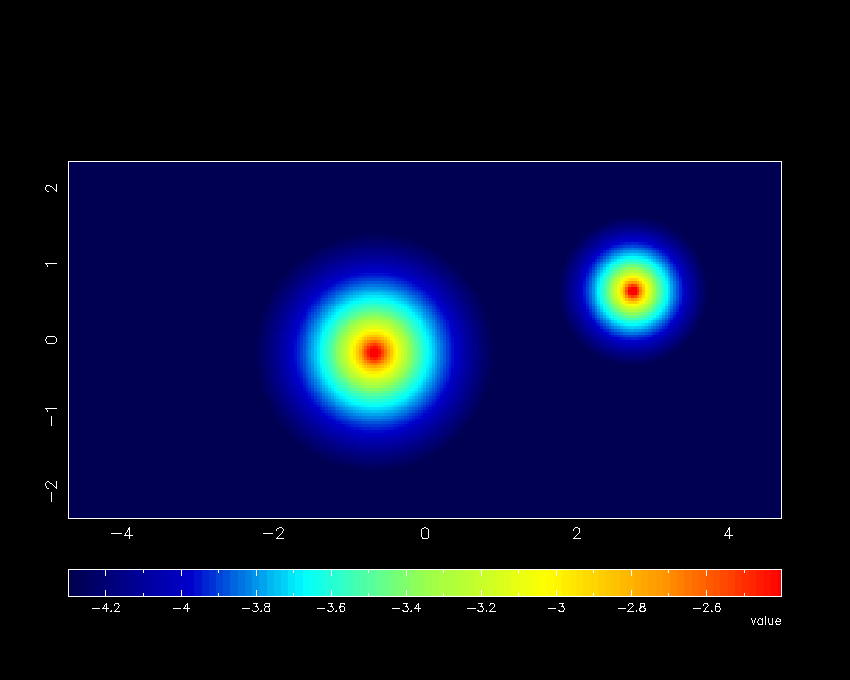
宇宙航空研究開発機構(JAXA)は11月24日、X線天文衛星「すざく」が、「Abell2256」という銀河団をX線で観測し、大小2つの銀河団が秒速約1500kmの速度で衝突している証拠を捉えたことを発表した。この測定は、銀河団プラズマ同士が衝突・合体している現場を世界で初めて直接的にとらえたものだという。同成果は、宇宙科学研究所の田村隆幸 助教、および大阪大学の林田清 准教授、上田周太朗 同大学院生、長井雅章 同大学院生などの研究グループによるもので、2011年11月25日発行の日本天文学会欧文研究報告(PASJ)「「すざく」+MAXI合同特集号(PASJ, vol.63, No.SP3」に掲載されることになっている。
宇宙の中で、星は銀河として集まり、銀河はまた銀河団という集団を作っている。宇宙最大の構造である銀河団からは1960年代にX線放射が見つかり、そこには星だけでなく高温のプラズマが存在することが発見された。その後の観測で、この1000万度から1億度という高温のプラズマの質量は星の総量を超えており、プラズマこそが宇宙にある(暗黒物質でない)普通の物質の最も主要な成分であることが判明した。
星よりも多くの質量をもつ星間物質をここまで高温に加熱することは容易ではなく、このプラズマがどのようにして加熱されたかを知ることは、宇宙の構造形成を探る上で鍵となることから各地で研究が進められてきた。多くの天文学者は、小さな構造同士が衝突・合体を繰り返し、より大きな構造へと成長する過程で、プラズマが加熱されたと考えてきた。
銀河団の衝突シミュレーション。2つの構造が衝突、合体してより大きな銀河団になる様子(数億年の進化)を計算機上で再現したもので、この画像は、プラズマの密度を対数表示したものとなっている(製作:山形大学の滝沢氏、出所:JAXA Webサイト)
言い換えると、銀河団のスケールでは大部分の質量を占める暗黒物質が持っている重力エネルギーが、プラズマの運動エネルギーを経由して、その熱エネルギーに変換されたことになる。これまでの観測では、プラズマの温度の分布はよく調べられてきたが、その元になったと考えられる銀河団プラズマの運動については、 X線画像の解析から衝撃波などによる銀河団プラズマの形状の微妙な変化から推定することしかできなかった。
今回、研究グループは、日本のX線天文衛星「すざく」を用いてこぐま座にある銀河団「A2256」を観測した。同銀河団は大小の2つのプラズマ構造を持ち、それらが合体する途中にあるようにみえる「衝突銀河団」の代表である。
「すざく」による銀河団「A2256」のX線画像。黒色と青色の2つの丸は「大構造」と「小構造」の位置を示す。左下の白い矢印は、角度の4.6分角(1度の13分の1相当)で銀河団の位置でおよそ100万光年の広がりを示す
左と同じ領域の可視光画像。ここに写っている銀河の一部が銀河団のメンバー(左および中央の画像の出典:Digital Sky Survey by the Space Telescope Science Institute)
X線画像(青)と可視光画像(赤)の重ね合わせ。この図の一辺は、18分角(銀河団の位置で約400万光年)(出所:JAXA Webサイト)
「すざく」のX線分光能力を用いて、銀河団プラズマからのX線輝線のドップラーシフトを測ることで、この2つのプラズマ構造の(地球と銀河団を結ぶ視線方向の)速度を精密に測定し、その運動状態をとらえることを目指したもので、観測の結果、これら大小の2つの構造はおよそ1500km/sの速度で衝突しており、数億年後には合体すると予想されることが判明した。
「すざく」による銀河団A2256の「小構造」の鉄ラインを含むX線スペクトル。横軸は、エネルギー。上のグラフの縦軸は、各エネルギーあたりのX線の強度(単位は、カウント/秒/KeV)。下のグラフの縦軸は、データとモデルの比。このデータによって、「小構造」の後退速度(赤方偏移)の精密測定を行った。(a)と(b)は、どちらも同じデータを誤差棒つきの十字で示されているが、データを再現するためのモデル(階段状の実線)が異なる。(a)の場合は、データを最も正しく再現するモデル。この場合、「小構造」は、「大構造」より小さな後退速度を持つ。一方、(b)の場合は、「小構造」が、「大構造」と同じ速度、すなわち、お互いに動いていないと仮定した場合のモデル。それぞれの図の下のグラフは、データとモデルの比を示す。(a)の場合は、データとモデルが良く合っているが、(b)の場合は、データとモデルにずれが見える。このようなデータ解析を通じて、「小構造」が「大構造」に対して、おおよそ1500km/sで運動していることが測定された(出所:JAXA Webサイト)
ドップラーシフトを用いて天体の速度を測ることは天文学の基本で、多くの天体で用いられているが、銀河団プラズマの速度を測定したのは今回の観測が世界でも初めてだという。これは、「すざく」に搭載されたX線検出器(CCD)の感度と、エネルギー決定の精度が世界で最高レベルであることから可能になったものだという。
今回の測定から得られた「大構造」と「小構造」の衝突を上から見た模式図(出所:JAXA Webサイト)
銀河団プラズマの速度を測定することは、少なくとも2つの意義があると研究グループは説明する。まず第一に、衝突・合体の証拠をつかみ、宇宙の構造形成の現場を直接的に調べることが可能となる。コンピュータシミュレーション上で宇宙の構造形成を再現し、その進化を見ることができるようになったが、実際に観測できるのは、それぞれの天体のスナップショットにすぎず、このスナップショットに、天体の運動、すなわち「動画」を加える事ができれば、進化の様子がより理解できることとなる。
これまでは、1つひとつの銀河の運動について、ドップラー効果を使って測定してきた研究はあるが、銀河の数はせいぜい百個程度であり、それぞれの銀河がどの集団に属しているかを判別することは、簡単ではなかった。また、銀河の集団とプラズマの集団が一緒になって動いているかどうかは、必ずしも自明ではないため、プラズマの運動を測り、すべての役者(銀河とプラズマ)を含む銀河団全体の3次元的な「動画」をとらえることが重要となっていた。
次に第2の意義として、プラズマの運動を測ることで、その運動を支配している暗黒物質の総量や分布に迫ることができるようになるという。地球やほかの惑星は、太陽の周りをそれぞれ異なる速度で回っているが、これは、惑星の遠心力と太陽の重力が釣り合っていることを意味する。同じように、銀河団の中でも、いろいろな力と暗黒物質の作る重力が釣り合っているはずであるが、これまではプラズマの運動を無視し、プラズマの熱的な圧力が重力と釣り合っている(熱的な圧力=重力)と仮定して暗黒物質の総量が推定されてきた。
しかし、もしも、プラズマが大きな速度を持って動いていると、この仮定は成り立たなくなる。例えば、プラズマが回転している場合では、熱的な圧力+遠心力=重力となり、これまで考えていた以上の暗黒物質が必要になることとなる。今回の測定は、「衝突銀河団」という特別な状態にある天体の結果であり、これまでにも、一部の研究者の間では、「熱的な圧力=重力」の仮定が成り立たない可能性が検討されてきた。
このようなプラズマの運動が、「普通の銀河団」でも存在するのか否か、これが次の課題であり、暗黒物質の分布を正確に知るためににどうしても必要な調査となると研究グループでは説明している。
宇宙には見つかっているだけでも1万を超す銀河団があり、その中にはいろいろな成長段階、すなわち運動状態を持つものがあるはずである。現在、日本が開発を進めている次世代X線天文衛星「ASTRO-H」には「すざく」のX線検出器比で20倍の高いエネルギー分解能を持つ新しいタイプのX線検出器(X線カロリメータ)が搭載される計画で、同装置を用いて銀河団プラズマの運動を系統的に観測することで、宇宙の大規模構造の成長の様子をとらえることが可能となり、その結果、それを支配している暗黒物質の謎に挑むことができるようになると研究グループでは期待を示している。
ルネサス、産業機器向けイーサネットPHY LSIを発売

ルネサス エレクトロニクスは11月24日、産業ネットワーク分野向けに、業界最小クラスの送受信遅延時間やケーブル診断機能などを付加したイーサネットPHY LSI「μPD60610GA」「μPD60611GA(IEEE1588 v2サポート版)」を製品化したことを発表した。2製品ともに単一インタフェース装置向けに開発されたもので、入出力が1本のタイプのシングルチャネル製品。2012年1月よりサンプル出荷を開始、量産は2012年4月より開始を予定しており、2013年4月には、月産10万個の生産を見込んでいる。
2製品ともに送受信回路の最適化により、ホストから受信した信号を次のネットワークに向けて送信するデータ処理遅延(レイテンシ)を従来品比で約35%低減している。また、産業ロボットなどにおいて求められるネットワークの迅速な接続、切断を達成するために、接続/接続処理の最適化を実施しており、同比約1/4の時間でのリンク確立を達成することが可能となっている。
さらに、通信品質を常時監視するケーブルモニタリング機能、信号の反射状況を調べてケーブルに発生した問題とその箇所を特定するTDR(Time Domain Refraction)機能を搭載したことにより、通信の高品質化とメンテナンスの容易化が可能となったほか、IEEE1588 v2に対応したμPD60611 GAでは、1ns精度のタイムスタンプを付加したパケットを送受信することで、高精度のクロック同期を実現しており、これにより複数の産業機器の同期制御とリアルタイム通信が可能となっている。
ルネサス エレクトロニクスの産業機器向けイーサネット PHY LSI「μPD60610GA」および「μPD60611GA」
JAEA、将来の核融合原型炉の設計指針となる核融合炉出力の決定因子を解明

日本原子力研究開発機構(JAEA)は、那珂核融合研究所にある世界最大級のトカマク型核融合実験装置(臨界プラズマ試験装置)「JT-60」のデータを詳細に解析し、核融合炉の高出力化の鍵となる、「プラズマが到達できる最大の圧力」を決める因子を解明したことを発表した。これにより、ITER(国際熱核融合実験炉)において目標とする出力を得ることがより確実となったという。同成果は、同機構 核融合研究開発部門の浦野創研究副主幹らの研究グループによるもので、国際原子力機関(International Atomic Energy Agency:IAEA)が刊行する制御熱核融合の研究開発全般を網羅する論文誌「Nuclear Fusion」に掲載された研究論文で、その年で引用度が高く、優れた成果に対し送られる2011年のニュークリア・フュージョン賞を受賞した。
高効率の核融合発電の実現には、燃料であるプラズマの圧力を高める必要があるため、境界プラズマに熱の流出を妨げる断熱層を形成して、プラズマ圧力全体を高める運転方式の研究開発が世界各国で進められているが、この断熱層形成の物理を解明し、適切な制御の指針を得ることが重要とされてきた。
これまで、断熱層の幅を決定する因子として、プラズマ内でイオンが磁力線に巻きついて運動する時の回転半径およびプラズマの圧力指数が考えられていたが、同じ燃料核種の場合、これらが一緒に変化するために、それぞれに対する依存性を分離することが困難であり、将来の核融合炉でのプラズマの到達圧力を高い確度で予測することができなかった。
研究グループは、重水素と軽水素の燃料核種の質量比により回転半径が異なることに着目して、JT-60で2種の核種での実験を行った。具体的には、回転半径のみを圧力指数から分離して変化させ、各々の断熱層の幅に対する依存性の解明を行った。
この結果、断熱層の幅の回転半径依存性が比較的弱く、一方で圧力指数の依存性が強いことが示されたという。。この成果は三重水素を使用する装置にも適用可能であり、現在フランスで建設が進められているITERでのプラズマの到達圧力の予測精度の向上に繋がり、目標とする核融合出力を得るために十分な幅の断熱層の形成が可能になるほか、将来の核融合原型炉の設計指針を与えるものになるという。
今回の研究成果の概要
IBM、最大100PFlopsの演算性能を実現可能なスパコン「Blue Gene/Q」を発表

IBMは2011年11月15日(米国時間)、これまで以上に高速で、エネルギー効率に優れ、信頼性の高い高性能コンピューティング・プラットフォームとして、Blue Geneスーパーコンピューター・シリーズの第3世代となる次世代スーパーコンピュータ(スパコン)プロジェクト「Blue Gene/Q」を発表した。
Blue Gene/Qは、技術者や科学者が取り組んでいる難問解決に活用され、ハリケーンの進路予測、海底の石油埋蔵地の特定、核出力性能のシミュレーション、遺伝子配列の解読などに役立てられると同社では説明している。
Blue Gene/Qは、1Wあたり2GFlopsという、高い電力効率を実現しており、これを搭載し、2012年にローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)で本格稼働する予定の「Sequoia」は最大20PFlopsの演算性能を実現可能なスパコンとなっている。
LLNLは、米国エネルギー省の国家核安全保障局(NNSA)が所有する総合国立研究所で、核実験禁止下での国家核抑止力の維持や、電力グリッドおよびネットワーク管理、エネルギーの研究や気候変動といった問題に対して、世界最速クラスのスパコンを適用してきた。IBMでは2011年12月上旬から、96台のラックの納入を開始するとしている。
また、米国アルゴンヌ国立研究所(ANL)も経済成長促進や電気自動車向けバッテリーの設計、気候変動の研究、宇宙の進化の解明などの分野における米国の競争力を向上させる目的でBlue Gene/Qを活用し、「Mira」と名付けられた10PFlopsのシステムを構築することを計画している。
Blue Gene/Qは、新しいIBM PowerPC A2プロセッシング・アーキテクチャを採用することで、前世代機Blue Gene/Pのコア数から4倍の16個のコア(このほか、OSの管理系機能用に専用のコアと、もう1つ予備のコアも搭載)による並列処理と、最大100PFlopsまで拡張可能なスケーラビリティを有している。また、設置面積も小さく、省エネ設計が可能で、2011年6月に発表されたGreen500で、世界で最もエネルギー効率の良いスパコン選ばれているが、低遅延で、高性能なプログラム実行によって、プログラムのエラーの解析や性能最適化を効率よく行うことが可能であり、それらは、すべてオープンソースと標準の動作環境下で提供されているという。
また、冗長設計に基づいて少数の可動部品で構成されているため、信頼性の面でも、同等クラスのスパコンと比べても高い値を示すことが可能だと同社では説明している。
Blue Gene/Qシステムの外観
Intersil、低電圧・低消費電力・低ノイズのDCPを開発

Intersilは、低電圧、低消費電力、低ノイズ動作を実現したシングル/デュアル/クワッド回路構成の、DCP「ISL233x5」および「ISL234x5」ファミリを発売した。
2ファミリはともに、電圧設定や抵抗設定を必要とするさまざまな用途に最適な、自由度と信頼性の高いポテンショメータ・ソリューション。動作電圧5Vでの消費電流は一般的な競合製品と比べて40%から50%低い2.8μAに抑えられている。
アナログ電源電圧は1.7Vから5.5Vの範囲に対応している。デジタルインタフェース用電源(VLOGIC)電圧は1.2Vから5.5Vの範囲に対応しており、制御に使用するマイコンが低電圧デジタルインタフェース出力しか備えていない場合でもレベルシフタは必要なくなっている。ワイパー・ポジションはI2CインタフェースまたはSPIインタフェースから設定する。また、ESD定格は人体モデルで6.5kVと高くなっている。
総抵抗は10kΩ、50kΩ、100kΩラインナップしている。これらのデバイスは3端子ポテンショメータまたは2端子可変抵抗器として使えるように設計されており、医療機器、ネットワークカード、スマートフォン、レギュレータ電圧マージニング回路のほか、較正やデジタル制御を必要とするアプリケーションに最適となっている。
ISL233x5は4個のDCPを一本のI2Cバスに接続できるように複数のアドレス・ピンを装備。ISL234x5は単一のI/Oラインに複数のDCPをリンクできるようにSPIのデイジーチェーンに対応している。
シングル回路構成品は10ピンのmicroTQFN およびMSOPパッケージで供給され、単価はで0.68ドル。デュアル回路構成品は14ピンまたは16ピンのmicroTQFNとTSSOPパッケージで供給され、単価は0.97ドル。クワッド回路品は20ピンのQFNおよびTSSOPパッケージで、単価は1.37ドル。価格はいずれも1000個受注時となっている。
IntersilのDCP「ISL233x5」ファミリと「ISL234x5」ファミリ
