仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日立、パワーモジュールの小型化に貢献する直接水冷型両面冷却技術を開発

日立製作所と日立オートモティブシステムズは、電気自動車(EV)/ハイブリッド自動車(HEV)用インバータの心臓部であるパワーモジュールの小型化に寄与する、直接水冷型両面冷却技術を開発したことを発表した。同技術を応用して試作されたパワーモジュールは、同社の従来の製品と比べて放熱特性が35%向上しており、床面積を50%に低減できることが確認されている。
近年、環境問題やエネルギー問題が背景にあることから、EVやHVなどが普及しているのは誰もがしるところ。しかし、それらに対してより広い車内居住空間やさらなる燃費の改善が求められているのが実情だ。
そのニーズに応えるためには、EVやHEVのキーコンポーネントの1つである車載用インバータの小型化が必要である。車載用インバータを小型化するには、多くのパワー半導体が集積されているパワーモジュールの放熱技術を開発し、冷却性能を高めることが必須だ。
そこで、両社はパワーモジュールの発熱を直接冷却水へ放熱させる水冷方式を選択。そして今回、独自の直接水冷型パワーモジュールの発表となったのである。
今回試作したパワーモジュールは、従来のパワー半導体を片面放熱から両面放熱構造とすることで放熱経路を拡充。具体的には、パワー半導体の両側に放熱経路を形成するためのグリースを用いず、絶縁層を介して放熱経路を形成することで冷却性能を向上させると共に、熱流体、電気発熱、応力などの解析技術を駆使した最適な放熱構造などの設計技術により小型化を実現した。
今後も、両社はEVやHVのキーテクノロジーとして、インバータに加えてモータやバッテリなどの中核コンポーネントのさらなる性能向上を目指すとしている。
なお、今回試作した直接水冷型両面冷却パワーモジュールは、12月3日から一般公開となる第42回東京モーターショー2011に出展する予定だ。
画像1。直接水冷型両面冷却パワーモジュールの試作品
理研、DNA修復酵素「MutL」の機能制御に必要な重要箇所を発見

理化学研究所(理研)は11月22日、DNAの損傷を修復して細胞ががん化することを防ぐ酵素「MutL」の、機能制御に重要な箇所を新しく発見したと発表した。発見は理研放射光科学総合研究センター飯野均特別研究員や倉光成紀グループディレクターらによるもので、成果は米科学雑誌「The Journal of Biological Chemistry」12月9日号に掲載される予定で、それに先だち日本時間12月3日付けのオンライン版に掲載される。
紫外線や放射線などの外的要因や、細胞分裂の際の複製エラーといった内的要因によって絶えず損傷を受けているのがDNAだ。そのため、DNAはさまざまな種類の損傷修復機構を備えている。
中でも、複製コピーでの間違えた組み合わせを見つけ出して除去することで修復する「ミスマッチ修復系」が機能しなくなると、大腸や子宮内膜、卵巣、胃など多臓器でのがんの発症リスクを高める遺伝性疾患の「リンチ症候群」になることが知られている。
DNAは、相補的2本鎖構造により、その遺伝情報を保っているが、複製エラーが起こると、遺伝子配列にミスマッチな部分が生じてしまう(画像1)。ミスマッチ修復系には、DNAのミスマッチ部分を見つけ、どちらが正しい配列かを判別し、エラー配列を持つDNAだけを切断し、正しい配列のDNAを相補鎖に合わせて合成するという複数の能力が必要となる。そのため、複数種類の酵素が協調して働く巧妙なメカニズムが存在するものと推測されている次第だ。
画像1。DNAの複製エラーによってミスマッチ部分が生じる仕組み。正常なDNAは相補的2本鎖構造を取っており、アデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、チミン(T)の4種類の塩基は相補的塩基対(A-T、G-C)を形成している。しかし、DNAの複製エラーによって、画像中のG-Tの例のようにミスマッチな塩基対が生じる場合がある。これを除去し修復するのがミスマッチ修復系だ
MutLはミスマッチ修復系の中で中心的な役割を担っている酵素であることから、ミスマッチを見つける酵素や正しい配列を判別する酵素と相互作用しながら、エラー配列を持つDNAだけを切断していると予測されている(画像2)。MutLは通常、正常なDNAを切断してしまわないように抑制され、適切な場合だけ働くように制御されているはずだが、その仕組みが不明な点が多い。
画像2。ミスマッチ修復系におけるMutLの働き。MutL(青)は、DNA上のミスマッチ部分を見つける酵素(緑)と、2本鎖DNAの内どちらがエラー配列なのか認識する酵素(黄)と連携しながら、エラー配列のDNAだけを切断する。MutLのDNA切断活性は、通常は抑制されているが、適切な場合(4の状況)にのみ機能を発揮するように調節されていると考えられている
これまで、MutLやミスマッチ修復系の研究は、主に大腸菌やヒトの酵素を用いて進められてきたが、大腸菌のミスマッチ修復系は他の生物とはMutLの機能が異なるという問題があり、一方のヒトの酵素は不安定で壊れやすく生化学的な実験に向いていないという問題があった。
そこで研究グループは、全生物の共通先祖に近いといわれ、1998年にゲノム解析が終了した超好熱性細菌「アクイフェックス」のMutLの機能解析を行うことにしたのである。アクイフェックスのMutLは、ヒトと基本的な機能が同じ上に、安定していて壊れにくいことから、選ばれたというわけだ。
MutLは2つの分子が結合した形を取る酵素だ。1分子中にATP(アデノシン三リン酸、生体内で用いられるエネルギーのほとんどを媒介する)が結合する部分を持つ「ATP結合ドメイン」とDNAを切断する役割を担う「エンドヌクレアーゼドメイン」の2つのドメインを持つ。そして、エンドヌクレアーゼドメインを介して2分子が結合している(画像3)。ドメインとは、酵素などのタンパク質は約20種類のアミノ酸が直線上に連結しているが、それらがヒトかマリになった単位のことを呼ぶ。
画像3。MutLの分子構造モデル。MutLは1分子中にATP結合ドメインとエンドヌクレアーゼドメインを持ち、2分子(赤と紫)がエンドヌクレアーゼドメインを介して結合した形を取っている。ATP結合部分(オレンジ)にATPが結合したり、外れたりすると、ATP結合ドメイン全体の形が変わり、亜鉛結合部分(黄緑)を介してDNA切断活性部分(水色)を制御すると考えられている
これまでに研究グループでは、ATP結合ドメインがATPの結合をスイッチにしてエンドヌクレアーゼドメインのDNA切断活性を制御していること、すなわち「ATPが結合しているとDNA切断活性が抑制され、ATPが外れた時(外れている時)に逆にDNA切断活性が促進されること」、「ATP結合に伴ってATP結合ドメインの形が構造変化していること」、「エンドヌクレアーゼドメインには亜鉛結合部分があり、この部分がATP結合ドメインとの仲介に必要なこと」を明らかにしてきた(画像3)。
研究グループはMutLにATPが結合することによってDNA切断活性が抑制される仕組みをさらに詳細に知るため、重水素交換法と質量分析法を組み合わせた手法を用いて、ATP結合が引き起こす構造変化が2つのドメイン間の接触をどのように変化させるかを解析。その結果、機能に関わると思われる新規領域の特定に成功したのである(画像4・A、B)。
画像4。MutLのドメイン間接触領域。(A)ATP結合ドメイン中のエンドヌクレアーゼドメインとの接触領域。(B)エンドヌクレアーゼドメイン中のATP結合ドメインとの接触領域。(丸囲み)2分子(赤と紫)のMutLが交差しながらエンドヌクレアーゼドメイン中で結合した部分。DNA切断活性に必要な箇所(紫)とDNA切断活性部分(赤)が機能する位置関係になるためには、2分子のMutLが結合している必要がある
さらに、ATP結合ドメイン中の領域(画面4・A)の周辺と、エンドヌクレアーゼドメイン中の領域(画像4・B)の一部に、ヒトを含めた多種生物のMutLが共通に持っている推定機能箇所をそれぞれ発見した。
これら2つの推定機能箇所は、ATP結合ドメインとの仲介に必要であるとされる亜鉛結合部分(画像3・黄緑)と、DNA切断活性部分(画像3・水色)に近接しており、これまでに研究グループが明らかにしてきた知見を裏付ける結果となったのである。
続いて、2箇所の推定機能箇所を欠いた、もしくは異なる種類のアミノ酸に置換したMutL変異体を作成して評価したところ、ATP結合ドメインが持っているはずの制御機能やエンドヌクレアーゼドメインが持っているはずのDNA切断活性が失われることを確認した。
MutLの2分子は、エンドヌクレアーゼドメイン中の推定機能箇所で交差しながら結合していたことから、DNA切断活性を発揮するためには、2分子が結合する必要があることも明らかになったのである(画像4の丸囲み)。このことは、どのようにしてMutLが2本鎖DNAの内のエラー配列を持つ方だけを切るのか、というミスマッチ修復系メカニズムの本質と関わりがある可能性を持つ。
また、実際にリンチ症候群の原因になった遺伝子異常箇所と照らし合わせたところ、この推定機能箇所(画像4のB)に生じた遺伝子異常がリンチ症候群の原因の1つであることも判明した。つまり、この箇所の異常はMutLのDNA切断活性を失わせ、DNA修復系を機能不全に導き、結果的にリンチ症候群を引き起こすものと考えられている。
研究グループは、今回の発見でMutLの活性制御機構で重要な役割を持つ箇所が明らかになったことから、今後はMutLが具体的にどのようにエラー配列を持つDNAに結合して切断するのかについて、分子機構レベルで解明を目指すという。そしてミスマッチ修復系で協調して働くMutL以外の複数酵素トドのように関係しているのかを明らかにし、ミスマッチ修復系のシステム全体を解明していく。それらの研究の過程で、リンチ症候群の新しい予防法や治療法の発見も期待できるとした。
さらに、DNA修復機構は全生物が共通に持っている生命現象の根幹的なシステムの1つであることから、仕組みの全体を解明することで、原初の生命からヒトまで全生物の基盤的な仕組みを深く理解できるようになるともしている。
WRO 2011 アブダビ国際大会

11月19日・20日にアラブ首長国連邦の首都アブダビにおいて開催された、WRO(World Robot Olympiad)2011国際大会で、レギュラーカテゴリー高校生部門に出場した愛媛県立八幡浜工業高等学校のチーム「YTH50 Endless evolution」が、金メダル(1位)を獲得した(画像1・2)。2007年の同部門で磯子工業高校の「X磯工」が獲得して以来の表彰台の頂点である。
画像1。YTH50 Endless evolutionの表彰式の様子。中東ならではの雰囲気
画像2。金メダルを獲得した、愛媛県立八幡浜工業高等学校のYTH50 Endless evolutionの3名。スポーツの世界だけでなく、エンジニア系の世界でも日本の若い世代が世界で活躍しているのは嬉しい
WROは、青少年の創造性と問題解決力育成を目的に、シンガポール国立サイエンス・センターの発案で2004年からスタートしたロボット競技会。使用するのは、世界のどの国でも入手しやすいということから、レゴ・マインドストームNXTもしくはRCXで、チームを組んで競技に挑むことになる。
今年の国際大会は、32カ国の代表300チーム以上が参加して開催。日本からは9月に開催されたWRO Japanの決勝大会で選抜された(各部門の優勝~3位などの上位チーム)小学校から高校生までの19チームが挑んだ。
競技は大別して2種類。自律型ロボットの制御を競う「レギュラーカテゴリー」(小・中・高校生の3部門に分かれる)と、NXTかRCXも利用した展示物を作ってプレゼンテーションを審査員に対して行う「オープンカテゴリー」(こちらの部門は1つだが、実際には小中高それぞれ別個に順位付けが行われる)だ。なお、トライアル競技としてサッカーや、高校生以上の学生をすべて対象とする大学生エキジビションも実施された。
レギュラーカテゴリーは、ロボットに自律的に作業をさせて与えられた課題をこなしていくのだが、小・中・高でロボットが活躍するステージの難易度が異なる。YTH50 Endless evolutionが金メダルを獲得した高校生部門は、「リサイクルロボット」というもので、制限時間120秒以内に8個のオブジェクトを指定された特徴に応じて仕分けして置いてくるという内容だ(画像3)。ちなみに中学生部門は「階段攻略」、小学生部門は「誘導ロボット」となっている。
画像3。競技中の様子。自律型の競技のため、事前にすべて準備を終えておき、後はロボットに託すだけ。競技中は見ているだけなので、なかなかハラハラする
また、そのほかのチームの成績は、レギュラーカテゴリー小学生部門で2チームが入賞(4~8位以内)し、同高校生部門で1チームが入賞。オープンカテゴリー中学生部門で1チームが入賞、同高校生部門で1チームが入賞した。今回は、金メダルが1、入賞が5と日本チームが健闘した結果となっている。
国内の参加チーム数が毎年増加しており、ここ数年は少なくても複数のチームが国際大会でも入賞を果たすようになった。今回も日本のレベルが高くなってきたことを世界にアピールできたのではないだろうか。
Silicon Labs、HDラジオ技術搭載車載用チューナIC「Si476x」ファミリを発表

米Silicon Laboratories(Silicon Labs)は、車載用チューナIC「Si476x」ファミリを発表した。同ファミリは、同社の車載グレード・ラジオ・チューナ製品ラインナップの最新製品で、価格重視のエントリーモデルおよび中位モデルのラジオ設計をターゲットとしたSi474xおよびSi475xチューナ・ファミリを補完する製品となり、プレミアムグレード、性能重視の車載ラジオおよびヘッドユニットの要求に対応している。
同ファミリは、同社の特許であるデジタル低IFテクノロジーを採用し、従来品では外付けだったほとんどの部品を集積した1チップCMOS ICソリューションである。優れたRFダイナミック・レンジとマルチパス・フェージングに対する耐性を実現し、分離度、感度、IMD3ブレイクイン、感度減衰、微弱信号処理、ダイナミック・チャネル帯域幅制御、先進のデュアルチューナFM位相ダイバーシティ受信といった重要な性能の水準が向上している。
また、拡張可能なマルチチューナ設計をサポートするモジュラ・アーキテクチャにより高い柔軟性を有し、AM/FM、小規模FM、長波(LW)、短波(SW)、NOAA天気ラジオ、FM RDSデコード、AMFM HDラジオ受信といった世界すべてのラジオ放送帯域をサポートしている。HDラジオ技術を開発したiBiquity Digital Corporationの認証も取得しており、今後の成長が期待されるHDラジオ市場に向けた強力なソリューションとなる。
なお、同ファミリは現在6×6mmの40ピンQFNで提供され、サンプルおよび量産数量を供給可能となっている。車載グレードの価格は、1万個出荷時の単価が11.62ドルから。車載機器メーカー向けの評価ボード「Si4763LNA-A-EVB」および「Si4767PD-A-EVB」も供給中で、価格は450ドルとなっている。
Silicon Labsの車載用チューナIC「Si476x」ファミリの活用イメージ
JAXA、金星探査機「あかつき」の金星再会合に向けた3 回目の軌道制御を実施
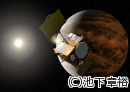
宇宙航空研究開発機構(JAXA)は11月21日、金星探査機「あかつき」の金星再会合に向けた軌道制御運用として、姿勢制御用エンジン(RCS)による第2回目となる近日点軌道制御を2011年11月21日13時57分(日本時間)から342秒間実施したことを発表した。
なお、同制御実施後の「あかつき」の状態は正常だとJAXAでは説明しており、今後は取得したテレメトリデータの解析および軌道決定を行い、金星再会合に向けた運用を継続していくとしている。
姿勢制御用エンジン(RCS)を用いた軌道制御の概要(出典:宇宙開発委員会報告資料)
