仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
タイ高速鉄道で日中競争が過熱、日本は低金利融資で対抗=中国ネット「こうなったら中国は無償援助を!」「タイにも意図がある」

2015年3月3日、タイの高速鉄道建設プロジェクトをめぐって日本と中国が競争を繰り広げており、日本がタイに低金利の借款を実施しようとしている。
【その他の写真】
日本は新幹線の技術をタイに提供すると同時に、ODAによって建設資金を提供することを計画しており、中国が提供しようとしている資金を大幅に下回る1%という低金利となっている。
このニュースが報じられると、中国版ツイッター・微博(ウェイボー)に次々とコメントが書き込まれた。
「こうなったら中国は無償援助をするしかない」
「もう無利子でしか対抗できない」
「中国は利息だけもらって、元金は免除すれば対抗できる。単純な話だ」
「中国政府はなぜ無利子借款をしないのか。友好国には気前が良いはずではなかったのか」
「競争が激しくなってきた。政府要人に袖の下を渡して堕落させよう」
「日本が勝つなら、民主と技術の勝利。中国が勝つなら、利益度外視で面子の勝利だ」
「中国人、自信なさすぎだろ…」
「日本は256キロの路線を設けるのに10年かけたが、中国は毎年その数十倍も延伸している」
「日本の新幹線はローカルネットワークだが、中国高速鉄道はアジアのインターネットのようなもの。新幹線を選べば、タイは将来後悔するだろう」
「中国の勝利は間違いない。国営企業は国の財政が支えている。日本企業は価格面で対抗できるはずもない。タイに理性があれば中国の高速鉄道を選択するだろう」
「中国の高速鉄道は世界が認める高品質だが、ことは高速鉄道だけでなく、さまざまな利益がからんでくる。さらには東南アジア地域の経済政治にも影響するだろう」
「タイは、一般鉄道は中国に、高速鉄道は日本にまかせることで、バランスを取ろうとしている。中国一国にアジアを縦断する路線を建設させない意図がある」
「日本の高速鉄道こそ本場の本物。技術も間違いない。そこが最大の問題」
「高速鉄道で最も重要なのは制御システムだ。日本の電子工業が極めて発達していることは誰もが知っている。新幹線が開通したのも中国よりも早い。日本は技術と資金面で中国を市場から排除しようとしている。実力の世界だ」(翻訳・編集/岡田)
中国当局、尖閣諸島専用ウェブサイトの日本語版の運用を開始―中国紙

2015年3月4日、人民日報によると、同日午前、中国で尖閣諸島(中国名:釣魚島)の専用ウェブサイトの英語版と日本語版の運用が開始された。
【その他の写真】
報道によると、同サイトは昨年12月30日に正式に運用が開始され、「釣魚島およびその付近の島しょが中国固有の領土である有力な証明」が記載されているという。(翻訳・編集/北田)
日本式の腐敗・・補助金企業の政治献金問題が安倍首相にも波及―中国メディア

安倍晋三首相が代表を務める政党支部が2013年、経済産業省の補助金交付が決定していた大手化学メーカー「宇部興産」などから献金を受けていたことが分かった。国の補助金を受ける企業による違法な政治献金問題が首相にも波及した形で、中国紙・環球時報は4日、“日本式の腐敗”だと指摘している。
同紙は日本メディアの報道を引用し、国の補助金を受ける企業からの政治資金規正法に違反した政治献金の問題が、これまでに安倍内閣の閣僚で続々と発覚し、西川公也農水相が辞任したことを紹介。安倍首相は自身の問題について、「そうした企業が補助金を受けていることは知らなかった」と述べ、問題はないとの認識を示した。
環球時報は日本の専門家の見方として、「政治献金問題は日本の選挙制度にからむ“不治の病”であり、政治家と企業が結びついた日本の政治文化を示すもので、“日本式の腐敗”と言える」と伝えた。
(編集翻訳 恩田有紀)
安倍首相夫人と熱意共有=女子教育活動で―米大統領夫人
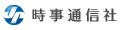
【ワシントン時事】ミシェル・オバマ米大統領夫人は3日、ホワイトハウスで開かれた女子教育の支援活動に関する会合に出席し、18〜20日の訪日について「女子教育への熱意を共有している安倍晋三首相の昭恵夫人を訪ねたい」と語り、訪日を楽しみにしていると述べた。
豪、コアラ7百匹安楽死 一部で増加、飢餓の恐れ

【カウラ共同】オーストラリア南東部ビクトリア州で2013~14年に、野生のコアラの数が生息域に対して過剰となり、一部が飢餓状態に陥ったため、数を減らす目的で約700匹がひそかに安楽死させられていたことが4日、分かった。オーストラリアのメディアが一斉に報じた。
コアラは入植者が毛皮のために捕獲し、20世紀初頭までに数が激減。特定のユーカリの葉しか食べないが、開発で生息地が狭まっている。保護団体によると、全国で推定10万匹を切り、絶滅の可能性も指摘される。ただ一部地区では数が増えすぎ、調整が必要との指摘もある。
